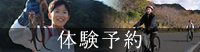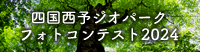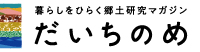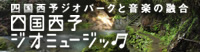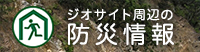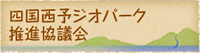石灰を海外にも輸出していた「白い村」
明浜町高山地区は南面に宇和海を臨み三方を急傾斜に囲まれた集落です。その大地は東西に横切る「仏像構造線」を境に、「秩父帯南帯」と「四万十帯」と呼ばれる地質体で構成されています。地面を掘ると、大規模な石灰岩ブロックや玄武岩、チャート、泥岩、砂岩などが出てきます。
ここでは古くからイワシ漁の漁村が成立し、戦国時代の宇都宮正綱の所領下では海を注視する軍事的機能を備えた拠点でもありました。江戸時代後期に畑の肥料としての石灰の利用が始まると、宇都宮角治によって高知から石灰業の技術がもたらされました。集落近くに石灰岩体が分布したことや焼成技術の改良も相まって、明治時代に生産量は向上。各所の石灰窯から白煙がのぼる様子から、当時の高山は「白い村」と呼ばれることもありました。最盛期は朝鮮半島や台湾へ出荷し、人口も増えてで住宅が密集するようになりました。しかしながら、化学肥料の普及とともに衰退し昭和57年に最後の工場が閉鎖、産業としての終焉を迎えました。
現在の景観には高山を構成する自然とともに、集落、段畑、道、石灰窯、鉱山跡、建造物、石造物、若宮神社、潮垢離等、地域の文化が良く残されています。