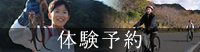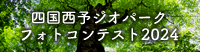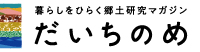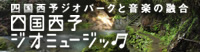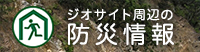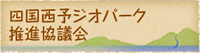活動アルバム
活動アルバム


市内外の皆さんに四国西予ジオパークを理解していただくため、イベントや研修会など様々な取り組みを行なっています。ここではこれまで実施してきた活動の記録をご紹介します。
「早春の城川で野鳥を見よう2025」を開催しました。
3月1日に「早春の城川で野鳥を見よう2025」と題した野外観察会を実施しました。
講師は日本野鳥の会愛媛の松田久司さまです。
前日や翌日の雨模様とは打って変わっての快晴。
城川町を中心に県内各所から参加者が集まりました。
まずはジオミュージアムの前で、双眼鏡や望遠鏡ののぞき方を練習します。

目標物を正しいのぞき方で見れるようになったり、ピント調整ができるようになったら観察のスタートです。
鳥たちが羽を休める木々が近くにたくさんある、城川歴史民俗資料館やギャラリーしろかわで観察します。
「“チチチチチチ” や “ギー、ギー” って音で鳥たちが鳴いているのが聞こえるかな?」
松田さんからのアドバイスを受けると、それまで意識していなかった鳥たちの鳴き声に、参加者の皆さんは気づきました。
鳴き声はよく聞こえるけど姿は見えない、ということで観察場所を変えることに。
すると、下相の住宅地を抜けたところでスズメやセグロセキレイ、カワラヒワを見かけることができました。
↑カワラヒワ(写真中央部分)
カメラに収めることはできませんでしたが、セグロセキレイは水浴びをしている最中で、
双眼鏡で観察することのできた参加者はとても喜んでいました。
その後場所を変え、県道197号線を歩いていると今度はモズとトビに出会いました。
↑モズ
↑トビ
道の駅「きなはいや しろかわ」の駐車場から黒瀬川の河原を見下ろすと、今度はキセキレイを発見。
春になると川辺などに飛び始めるユスリカの仲間を食べるために、河原を歩き回るのだそう。
最後は四国西予ジオミュージアムへ戻り、出会った鳥の種類を皆さんで確認します。
この作業を「鳥合わせ」といいます。

この日は合わせて14種類の鳥を観察することができました。
松田さんによれば、例年のこの時期に見られる城川の鳥の種数としては、少ない方だそうです。
渡り鳥は、地域の中のちょっとした変化によって、飛来数が大きく変化するとのこと。
例えば、平成30年豪雨で被害を受けた肱川流域では、復旧のための河川整備工事によって、川岸に生えているヨシなどの高茎の植物が一時期数を減らしました。
このことによって次の2つの変化が生じました。
①ヨシの群落の陰に隠れて営巣するホオジロの仲間がいなくなる
②ヨシなどの茎の中にはカイガラムシの仲間が入っているが、それを食べているシジュウカラやメジロ、エナガなどが来なくなってしまう
現在は目撃例も例年並みに戻りつつあるということです。
「河床掘削は復興のために必要なことだけど、区域を区切って実施したりすると鳥たちにもストレスをあまりかけないやり方になるんじゃないかな。」と松田さん。
逆に、地球温暖化のような大きな環境変動による影響などは、20~30年ほどの長期的な記録を取らないと判断ができません。
参加者の皆さんは松田さんから、継続的に野鳥の観察記録をとることの大切さを教えてもらいました。
今回の観察記録は日本野鳥の会愛媛で管理しているデータベースに反映され、鳥や環境変動を研究している方のために役立てられます。
四国西予ジオミュージアムでは今回を皮切りに、できる限り毎年野鳥の観察会を実施していきたいと考えています。
(事務局:S)